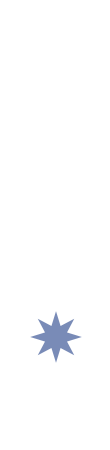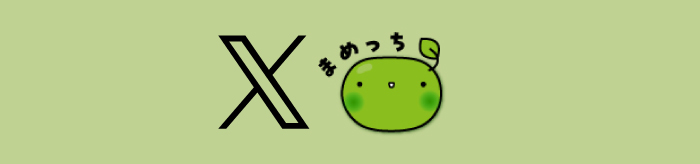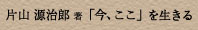神宗
炊き立てのごはんのお供やお弁当のおかず、お茶請けとして親しまれてきた昆布の佃煮や塩昆布。天然素材を使い伝統の製法に準じて作る神宗の味は、関西を中心に人々の食を豊かに盛り上げてきました。創業以来230年変わらないおいしさの秘密に迫ります。

神宗
大阪府大阪市中央区高麗橋3-4-10(本店) 06-6201-2700
http://www.kansou.co.jp/
1781年、大坂の靱にて海産物問屋として創業。代々の店主が厳しい目で選び抜いた素材を使い、自然のうま味を引き出す独自の加工法で商品づくりに励む。北海道道南産の天然真昆布をじっくり炊き上げた佃煮や塩昆布は、同社を代表する味。大阪の銘品としてお土産にも重宝されている。現在は「素にして上質」を企業理念に掲げ、原点を見つめながら新たな発想でまい進を続ける。
神宗の歴史をたどる

昔の神宗本店。厳しい目で材料を厳選し、品質に対して妥協を許さない姿勢はこのころから培われてきたものです。
大阪随一のオフィス街、淀屋橋に本店を置く神宗。塩昆布や佃煮を看板商品とする関西の老舗です。近代的なビルの1階にありながら、本店の佇まいは江戸時代の商店さながら。瓦屋根やガス燈を配した凝った造りは、味と共に受け継いできた大坂町文化の風情を今に伝えています。
神宗の歩みは1781年、大坂の靭に始まりました。江戸時代の大坂は天下の台所と呼ばれ、北海道からの北前船が行き交い、昆布をはじめとしたさまざまな食材にあふれていました。町では商売が盛んで活気に満ち、初代・神嵜屋宗兵衛氏も海産物問屋として看板を掲げます。数々の商品の原型が生み出されたのは嘉永年間に本店が京町堀へと移ったころ。海産物を並べる傍らで販売していた佃煮や塩昆布がいつしか評判の味になっていました。明治時代に入ると町中では昆布佃煮の専門店も見られるようになったことから、本腰を入れて加工食品を手掛けるようになり、現在の発展へとつながっています。
天然真昆布へのこだわり

神宗を代表する商品である昆布の佃煮と神宗の味になくてはならない北海道道南産の天然真昆布。昆布だしに親しみの深い関西で重宝されています。
神宗の商品はどれも素材の良さを引き立てるシンプルな味わい。「自社で扱っているものは昆布にしてもかつおにしてもそのまま食べておいしいものばかり」と社長の小山鐘平さんは胸を張ります。とりわけなくてはならない素材が昆布。創業以来、北海道で採れた天然の真昆布にこだわってきました。
真昆布は利尻、羅臼と並ぶ3大昆布の1つであり、クリアで上品な甘味のある出汁がとれる高級品。そのうえ天然のものは身が引き締まって厚く、濃厚なうま味とコクがあるため加工品にも適しています。同じ道内産でも漁獲地や育ち方によって形や味、やわらかさが異なり、どれでもよいというわけではありません。神宗では天然のなかでも等級が高く真昆布ブランドとされている道南産白口浜の天然真昆布を使用しています。これがなければ神宗ならではの深みのある味を出すことはできません。
真昆布の産地の現状

マッカを器用に操り、真昆布を引き上げる漁師たち。北海道の過酷な環境にもまれることで立派な真昆布が育ちます。
「上質な真昆布が無事私たちの元へ届けられるのは、自然の力と産地の努力があってこそ」と小山さんは言います。昆布漁が行われるのは春から夏の終わりにかけて。好天の日には漁師たちが勇んで船に乗り込み、沖へと漕ぎ出していきます。手にしているのはマッカと呼ばれる竿。この道具を操り、海底に生えている天然真昆布を一つ一つ根元からねじり切ります。採取した昆布は干場という小石と砂利を敷き詰めた場所に並べ、太陽と潮風にさらして乾燥させます。乾燥を終えると選別の作業。色、ツヤ、形、厚さ、乾燥具合などを一枚一枚丁寧にチェックし、規格ごとに結束します。その後検査機関が格付検査を行い、合格したものだけが出荷を許されるのです。
真昆布は優れた漁場である道南地域でも現在8割が養殖で天然はわずか2割ほど。大変希少価値が高いことで知られています。天然の昆布は採取できる大きさに育つまでに時間がかかるうえ、近年は海水温の上昇や台風の影響などで採取量が大幅に減少。市場に出回る量がどんどん少なくなっています。神宗でも年々安定して確保することが難しくなっているそうです。
食の安全を守る戦い

昆布やちりめんじゃこ、山椒などの原材料や出来上がった製品は安全装置と厳しい人の目で異物混入を防いでいます。
昆布をはじめ、ちりめんじゃこや山椒などの素材を選ぶ際、神宗では味に力強さを持つ天産物であることにこだわってきました。その一方で徹底して取り組んできたことが安全・安心に配慮した品質管理です。ちりめんじゃこには網の一部や釣り針が入っていたり、山から収穫してきた山椒には小さな枝や土がついていたりもします。天産物を扱う上で異物が混じってしまうことは仕方のないこと。けれどもお客さんが口にする限り、それらが少しでも入っていることは絶対に許されません。
異物混入対策には万全の設備と人材を投資。製造の前段階で金属探知機やX線を使って原材料を厳しくチェックし、最終的には目視で確認して食の安全を守っています。また、原材料の原産地はすべて公開し、放射性物質の自主検査も実施して結果を公表。情報をオープンにすることで、毎日の食卓に安心を届けられるよう努力しています。
関西出汁の発展は水にあり

ノルウェーにあるオルデダーレン渓谷で生まれたオルデン水。美しい環境が育んだ水は曇りのない味です。
また神宗では出汁に使う水にも強いこだわりを持っています。水にはカルシウムイオンとマグネシウムイオンなどのミネラルが含有されていて、WHO(世界保健機構)では硬度が120mg/l以下を軟水、120mg/l以上を硬水と定めています。ミネラル分の少ない軟水は、口当たりがやわらかくうま味成分を引き出しやすいという特徴があり、出汁で煮炊きをする和食向き。ミネラル分の高い硬水は喉につかえるような硬さがある分しっかりした飲みごたえがあり、豚や鶏で取るスープに使うと灰汁(あく)が出てクリアな味になります。日本の水道水は軟水にあたりますが、関西と関東では硬度に差があります。東京が約65mg/lであるのに対し、大阪は約44 mg/lとやや低め。昆布は硬度が低い水ほうが上質な出汁が取れるため、関西で昆布出汁が普及した要因の一つではないかとも言われています。
神宗ではこうした水の特性に注目。大阪の水は軟水ではありますが季節によって水質に優劣が出るため、佃煮を炊くのに安定して同じ味を出すことができないという難点がありました。そこで目を付けたのがノルウェー産の「オルデン水」。約5000年の歳月をかけて地下でろ過された氷河水は非常に純度が高く、硬度は14 mg/lと究極の軟水です。
「水道水とオルデン水それぞれに昆布を浸けて出汁を抽出してみると、明らかに味が違い、オルデン水のほうが甘味を強く感じられます」と小山さんもその実力を絶賛します。神宗にとって水もまた、味を追求するうえで欠かせない素材の一つになっているのです。
再び味の原点に戻って

「細切り昆布」はそのまま食べるだけでなく、料理にうま味をプラスする調味料としての役割も担ってくれます。
東日本大震災をきっかけに神宗は新たに「素にして上質」という企業理念を掲げました。「素」は大自然の恵みを受けた日本伝統素材、「上質」は永遠に飽きることがない食の原点を意味します。つまりこの言葉には、古来より朽ち果てない食材を使って商品づくりを今一度見直し、日本で伝承されてきた本来の食の在り方を追求しようとする心意気が込められています。
「東日本大震災が発生したころは、ちょうど出汁パックを開発しようと研究に勤しんでいました。その中で加工食品の多くは化学調味料や酵母エキス、人工甘味料などで味が成り立っていることを知りました。当社では震災前までうま味調味料を使用してはいましたが、そのほかの不自然なものは一切使っていなかったので、世の中の加工食品に秘められた味の実態を知らなかったんです」と小山さんは振り返ります。確かに人工のものに頼れば簡単に味がまとまり、コストも抑えることができます。
「でも日本には天然のうま味があるじゃないですか。それを使わずして見せかけの味ではダメだと。もっと正直な商売をしなければいけないなと思いました」。
以来、うま味調味料は排除し、昆布や煮干しなどで取った出汁で昆布を炊き、日本酒を加えてふっくらと仕上げる昔ながらの家庭的な製法に立ち返りました。手間もコストもかかるやり方を貫くことはリスクとも背中合わせ。しかし、思いを込めて作ったまっすぐな味が売れることは、しょうゆや日本酒、かつお節を製造する日本の食の伝統産業にも良い連鎖を生むのではないかと小山さんは考えています。
味を支える昔ながらの製法

丁寧に出汁を取るところから始まる佃煮づくり。おいしさを追求するために手間暇は惜しみません。 職人は1人で複数の釜を担当し、火加減を見ながら愛情を込めて炊き上げていきます。
神宗の佃煮づくりは出汁となるかつおの本枯節を削るところから始まります。削るのはその日使う分だけ。削りたてならではの高い風味と香りを生かすためです。自慢の「オルデン水」をたっぷり使ってうま味を抽出し、雑味のない出汁に仕上げていきます。
炊き上げる作業は職人の手によって行われます。工場に並ぶのはなんと100口もの直火釜。一気に火にかけると室内の温度は急上昇し、夏場には熱中症になりそうなほど高温になります。そんな過酷な環境の中、職人たちは5時間も釜につきっきり。丁寧に取った出汁を昆布などと合わせ、様子を見ながらかき混ぜ火加減を微調整していきます。
素材が持つうま味と甘味を最大限に引き出せるのは、熟練の技があってこそ。手間を惜しまず愛情をかけて作られた逸品はふっくらとやわらか。滋味深い味が多くの人を魅了しています。
薄れゆく出汁文化

佃煮づくりの出汁に使うかつお節と煮干し。そのままでも食べられる極めて上質なものを厳選しています。
「昆布とかつおで出汁を取るなんて、昔も今も贅沢なことだと思うんです。それでも昔の人はがんばって手間をかけてきちんと料理を作っていました。ところが現代のお母さんたちは家事や子育て、仕事に忙しく、料理に時間をかけられなくなっています。その代わりに外食産業が盛んになり、冷凍食品やレトルトも進化してきました。手軽なものについ頼ってしまい、料理を作ることが義務になってきている女性も多いのかもしれません。だし教室でどんなに子どもたちが本物の出汁をおいしいと思ってくれても、家庭でお母さんが一から出汁を取ろうと思わなければ、その先の広がりはありませんよね。今の祖母世代も、カレーやオムライスなどがかっこいい食べ物だともてはやされた時代を経験し、家庭料理にも洋食の波が押し寄せました。出汁文化が根付いていないのは、こうした背景から昔ながらの日本の家庭の味が次の世代へ伝承されていないことが大きいと思います」。
女性ができないことは、男性が担えばいいというのが小山さんの持論。一般向けのだし教室では男性の参加者も多く、関心の高さに期待を寄せています。
学校での食育活動

小学校での「味の成り立ちを知る授業」。子どもたちは昆布・かつお節・煮干しの試食をしたり出汁の引き方などを学びます。
2013年に和食が世界無形文化遺産に登録され、昆布やかつお、煮干しを使った出汁の文化が世界で注目されている今。残念なことに日本の若者の和食離れには拍車がかかっています。今こそ正しい食文化の継承が大事だと、神宗では出汁のおいしさを伝える食育活動にも積極的に取り組んでいます。小・中・高校や大学などに出張し、生徒や保護者に向けて「だし教室」を開催。かつお節を自分の手で削ったり、昆布とかつお節だけで出汁を引き試食したり、出汁と水で溶いた味噌汁をそれぞれ飲み比べたりと、体験を交え楽しみながら学べる内容になっています。
指導を行っている小山さんは、昆布とかつおから取った出汁を飲んだ子どもたちが、一様においしいと言い笑顔になる様子を見てほっと胸をなでおろします。けれども家庭では便利な顆粒だしが主流。純粋な出汁の風味を知らずに育つ子どもが増えていくことに心配ものぞかせます。
食育は男性も担う時代

独自の製法でふくよかな味わいに仕上げたちりめん山椒も人気の品。ぴりりと利かせた山椒が味のアクセントです(写真上)。カフェで人気の煮汁ソフトクリーム。ほんのりと出汁のうま味が利き、さっぱりとした甘さです(写真下)。
「ほとんどの男性は昆布やかつおで出汁を取る方法を知らないので、だし教室で教わったことを純粋に受け止めてもらえているようです。私自身も料理好き。幼いころから父がキッチンに立つ環境が普通だったこともあり、それを受け継いでいるんだと思います」。
小山さんは自分が作ったものを家族に振舞うことも多いそう。家庭では子どもたちに特別な食育をしているわけではなく、日々の食卓から父親の目線で食の大切さを教えていると言います。
「食育というと難しくなりがちですが、私はただ私がおいしいと思うレベルのものを子どもに食べさせたいと思っているだけです。今の親世代が子どもにファストフードを与えるのは、親がおいしいと思っているからだと思います。日本で出汁を取る人がわずかな理由は外国人と同じで、丁寧に上質な素材で取った出汁のおいしさを知らない人が多いことが原因でしょう。経験がないのです。そんな時代ですから、普通に昆布やかつおで出汁を取っただけで、どの家庭にもまねができない食生活や教養を子どもに学ばせることができます。初めは手間かもしれませんが、慣れれば楽なものです。その手間だけでも男性がやってもいいと思いませんか」。
【コラム】海藻を消化できるのは日本人だけって本当?
日本人が習慣的に食べてきたのりやわかめなどの海藻類。欧米ではあまり食べる文化がありません。それには体にまつわる深い理由があることが近年の研究でわかりました。海藻を消化吸収するためには特殊な酵素が必要なのですが、この酵素を持つのは海に住む細菌の他に日本人の腸内だけ。研究グループの報告によると、日本人は昔から海藻が身近で、生のりを食べることで付着した菌が体内に入り、腸の中で遺伝子の受け渡しがあったからではないかとされています。優れた腸内環境を持つ日本人。適量を上手に摂取し、美と健康を保ちたいものです。