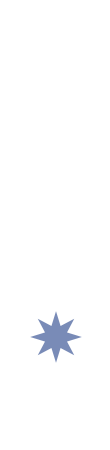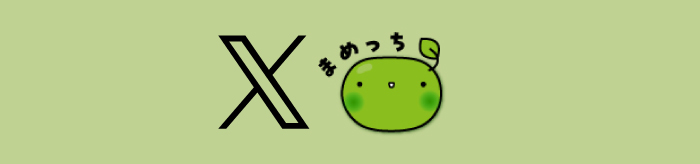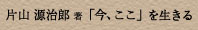料理研究家 坂本廣子さん
幼児期からの食育の大切さを長年提唱し続ける坂本廣子さん。NHK教育テレビ『ひとりでできるもん!』の指導や五感を使った子どものための料理教室『キッズキッチン』など、エポックメーキングな仕事の陰には「食を通して子どもたちに生きる力を身に着けてほしい」という坂本さんの堅い信念がありました。

食育・料理研究家 坂本 廣子さん
サカモトキッチンスタジオ
http://www004.upp.so-net.ne.jp/skskobe/
農林水産技術会議委員、相愛大学客員教授、神戸女子短期大学非常勤講師、キッズキッチン協会会長、近畿米粉食品推進協議会会長、伝統食品研究会理事、テンペ研究会理事。30代のときに新聞のレシピ連載『忙し母さんの手抜き料理』を2年間担当し、多くの女性たちから人気を集める。生まれ育った神戸を拠点に、食生活に関する講座や雑誌、新聞のコラム執筆等活動の幅を広げ、1991年から始まったNHK教育テレビの子ども向け料理番組『ひとりでできるもん!』を指導。現在は、社会問題を食から解決することをテーマに置き、TVや雑誌、新聞などのメディアをはじめ、商品開発や企画・講演、大学での指導など多方面で活躍中。著書は100冊を超える。
時代に新風を起こした番組
1991年にNHK教育テレビで始まった『ひとりでできるもん!』は、幼稚園児から小学校低学年の子どものための料理番組。放送開始当時は舞ちゃんという小さな女の子がメインを務め、ゲーム機から飛び出した料理名人のアニメキャラクター・クッキングにサポートされながら、毎回さまざまな料理を作るという内容でした。
夕方に放送されるわずか15分のプログラムながら、子どもが大人の手を借りず手際よく調理を進める姿と登場キャラクターのかわいらしさが反響を呼び、中高校生や若いお母さんたちまで、幅広い世代から支持されるようになります。やがて視聴率10%台を達成するほどの人気番組へと成長。時代の流れや視聴者のニーズによって内容を変えながら2006年まで放送され、15年間に渡り愛される長寿番組となりました。
『ひとりでできるもん!』が始まるまで、子どもが1人で包丁を握ったり、火を使い調理をすることは危険だとタブー視されていました。しかし、料理の創造性が子どもの教育に役立つと考えた番組スタッフたちは、あえてタブーを破ることに挑戦。そのスタッフの1人として活躍し、番組づくりの立役者となったのが料理研究家の坂本廣子さんです。
きっかけは1冊の著書から

キッズキッチンでは子どもたちが主役。エプロン姿がりりしく映ります。
NHKが前例のない番組づくりに孤軍奮闘していたころ、製作者たちの目に留まったのが坂本さんの著書『坂本廣子の台所育児~一歳から包丁を』でした。本書は、子どもを台所に立たせることの意味、道具の選び方や何から始めさせるのが良いかなどをアドバイスした1冊。米のとぎかたやだしの取り方、魚を焼くといった料理の基礎も、子どもの目線でわかりやすく丁寧に書かれ、家庭における食教育のバイブルとして今も読み継がれています。この本を読んだ製作側からのオファーを受け、坂本さんは『ひとりでできるもん!』に監修として携わることになりました。
当時は親子料理教室の全盛期。しかし坂本さんはその在り方に疑問を抱いていました。「親子で習うといっても、作業はほとんど親が進めて子どもは何もさせてもらえないのが常。ただ見ているだけでは子どもにとって何の経験にもなりませんよね」。
食を通しての学びが子どもの成長に大きく影響を与えることに気が付いた坂本さんは、1984年に「食教育を考える会」を発足。子どもが主役となって料理をする教室を幼稚園などで指導するようになります。活動の根底にあるのは「子どもが料理をすることはけっして難しいことではないし、危険なことでもない」という思い。『ひとりでできるもん!』の製作スタッフに加わったのは、こうした思いを、番組を通してより広く発信していけるのではと考えたからでした。
エデュテインメントとしての番組づくり
「私にお話があった段階ではまだ主人公しか決まっておらず、キャラクター設定もあいまい。子どもたちに誤解を与えないためには、どう表現し、どう伝えるのが一番いいのかをみんなで何度も何度も話し合いました」。しかし製作スタッフには男性が多く、坂本さんが女性や母親の立場で意見を述べると食い違いが生じることが日常茶飯事。最初に受け取ったパイロットもあまりにお粗末で、現実とかけ離れた内容に驚いたと言います。
「たとえば舞ちゃんがゆで卵を作るというシーン。まずはお鍋にお湯をたっぷり入れて…とあるわけです。問題はそこから。指をパチンと鳴らすと、お湯がなみなみと入ったお鍋が自動的に浮き上がり、シンクに移動するとされているんです。これって現実にはありえないことでしょう。テレビを観た子どもたちが本当に指をパチンと鳴らせて、体にお湯をかぶるようなことがあったら大変。ケガが続出しますよ」。本来なら、お鍋の近くにお水を入れたボウルを用意してお玉で卵を取り出すという安全に配慮した方法を書くべきところ。作り手である大人が番組のおもしろさを追求しすぎ、まったく子どもの気持ちになっていなかったことが、製作を進めていくうえで大きな壁となりました。「作り手には責任があります。子どもたちが観た通りに料理をできるようにしないと絶対にダメ。何より安全を最優先にということをお願いしました」。
坂本さんは番組が単なるエンターテインメントで終わってはいけないと強く思っていました。子どもたちの興味を引き付ける笑いや楽しさの部分はあくまでエッセンス。最終的に大事にしないといけないのは教育的視点だと。education(教育)とentertainment(娯楽)を融合したエデュテインメントとしての作り方を目指すことに、この番組の意義があると考えました。
食の通訳者としての役割

食材の姿に興味津々の子どもたち。生魚でも上手にさばきます。
台本に目を通すときは、子どもに予断を与える表現がないかにも気を配りました。「私の中でちょくちょく引っかかったのが『舞ちゃんは○○をしたからいいお嫁さんになれるね』というキャラクターのコメント。脚本を書いていたのは男性でしたから、女性は結婚すればいい、女性は家事をするものだという気持ちがどこかにあったのでしょう。でもこのコメントを女性蔑視と受け取る人もいます。子どもたちのためにこういう表現はやめてくださいとずいぶんうるさく言いました」。
また、お母さんに急な仕事が入って、舞ちゃんが1人でお留守番をすることになったシーンでも、坂本さんの鋭いアンテナが働きます。「舞ちゃんが家に帰ってくると机の上には500円玉が置いてあり、電話の留守電ボタンを押したら『500円で何でも買って食べてね』とお母さんが残したメッセージが流れるという設定になっていました。私としてはそこでもちょっと引っかかったわけです。働くお母さんの一人として経験から言わせてもらえば、お母さんたちはこんな安易な気持ちで仕事には出ていませんよと」。母親はどんなときも子どもが気がかり。けれども、その思いに寄り添っていないことに坂本さんは違和感を覚えました。
さらに、舞ちゃんのじゃまばかりするコンビキャラクターの設定についても核心を突く助言をピシャリ。「最初はマヌケなキャラクターのほうが関西弁をしゃべることになっていました。それも、関西人の私が聞くと不自然なイントネーション。これも受け取る側の子どもたちに『関西人はマヌケ』という間違った先入観を与えかねませんよね」。そんな激論を幾度も脚本家と重ねていくと、台本が真っ赤になることも少なくありませんでした。坂本さんはいつも自分のことを食の通訳者(食べる人と食べ物の橋渡し役、食をわかりやすく伝える人)だと言います。中途半端なことや間違ったことは伝えられないという通訳者としての信念が、番組づくりにも大いに生かされました。
活動の原点は手抜き料理
10代のころから食の安全に興味を持っていたという坂本さん。でも、食文化を伝える活動を自ら積極的に仕事にしようと思ったことはなく、求められるままに進んだだけと漏らします。転機は30代半ば。そのころの坂本さんは、子育て、主婦業に加え、書道を教えながら展覧会へ自分の作品を出品したりと多忙な日々を送っていました。時間に追われながらも加工食品は使いたくない、子どもたちに少しでも安全なものを食べさせたいとの思いから続けていた食材の共同購入。しかし野菜などを上手に使い切ることができず、やめていくお母さんたちが増えていきました。
そこで坂本さんは、どうすれば買った食材を無駄なく食べることができるかを周囲の人に教えるようになります。これがきっかけとなり、料理指導者としての道がスタート。「料理って大元を押さえてプロセスをつかめば、どこを簡略化できるかがわかるんですよ」。独自の考え方や手法を、やがて新聞でのレシピ連載『忙し母さんの手ぬき料理』で披露するようになります。手軽だけれど家族への愛がたっぷり詰まった坂本さんの料理は、多くの女性たちから支持されました。以来、考案したレシピは数えきれないほど。それでもネタは尽きることがないと胸を張ります。
海外で食文化を学び、同じ道に進んだ理系女子の長女と交わす雑談から、目からウロコのアイデアが生まれることも。「ひらめいたら即実践。夜遅く台所に立って実験することもあります」。尽きることのない好奇心と軽やかなフットワークが、坂本さんの活動の基盤です。
食体験を通して自信を育てる

包丁を持つ手はすでに一人前。見守りスタッフのサポートがあるからこそ親御さんも安心。
坂本さんが活動の拠点とするサカモトキッチンスタジオでは、五感で学ぶ子ども料理教室「キッズキッチン」を開催しています。これは料理のテクニックを教えるための教室ではなく、子どもたちが視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を使って調理を行うことで新しい自分を発見したり、新鮮な体験を積み重ねて豊かな感性を育むことを目的としています。また、食材と向き合うことで食べることへの積極性も養います。
対象年齢は2歳から小学校6年生まで。レシピは子どもの手や能力に合わせてアレンジし、細かな調理手順や方法もスタッフ間でデモンストレーションを重ね、ブラッシュアップします。調理実習中は安全に配慮し、1テーブル4人の子どもに対して2人の見守りスタッフがついてはいるものの、主役はあくまで子どもたち。スタッフのサポートは最小限に抑え、最初から最後まで自分の力でやり遂げます。「子どもに子どもだましはしない」のが坂本さんの信条。作る料理は大人も顔負けの本格派です。食材は旬を意識し、市場から仕入れた鮮度の良いものを使用。タチウオのシーズンには身を棒ずしにし中骨ですまし汁を、イカナゴが豊漁を迎えると、くぎ煮やかき揚げに挑戦するというから驚きです。
「粉を練ってピザ生地を作ることも、魚を三枚におろすのも子どもたちはお手のもの。お母さんでも嫌がるような手間のかかる作業を、みんな目をキラキラと輝かせながらやっていますよ。料理は子どもたちの見えない力を引き出してくれるんです」。
食教育で子どもに生きる力を

レシピのアイデアがひらめくと即実践。台所は坂本先生にとって大事な実験室です。
今の日本の子どもたちは、ニートの増加や学力低下などさまざまな問題を抱えています。その根底にあるのは自己尊厳感の低さだというのが坂本さんの見解。「今、高校3年生の95%以上が自分に自信を失っているというデータもあります。私が子どもたちに料理を教えているなかで学んだことは、どんなに大人が言葉で褒めても、子どもが自らの体験を通して自分自身を認められなければ、本当の意味での自信にはつながらないということです」。
子どもたちの自己尊厳感を高めるために大人ができるのは、幼いころからいろんな体験をさせて「やった!こんなに難しいことが自分にもできた!」という実感を積み上げることだと坂本さんは言います。そして、キッズキッチンがそのツールの一つになると続けます。「子どもたちには料理を通して、自分の人生を生き抜く力を身に着けてもらいたいというのが私の強い願い。子どもたちに生きる力とは何かを通訳していくのが私の役割だと思っています。『ひとりでできるもん!』で子どもたちがごく当たり前のようにキッチンに立てる環境を作ることができ世の中を変えられたように、キッズキッチンでもう一度世の中を変えることができたら、それが私の仕事のゴールなのかもしれません」。