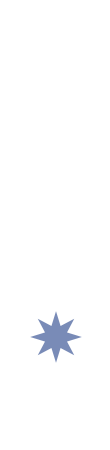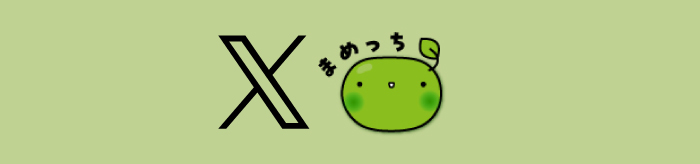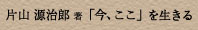京都第二赤十字病院
長い入院生活を送る患者さんにとって、食べたくても食べられなくなることは何よりつらいこと。生きることの証である「食事をしたい」という患者さんたちの願いを叶える、やさしいスープがありました。

京都第二赤十字病院
京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 075-231-5171(代)
http://www.kyoto2.jrc.or.jp
充実した医療設備を備え、安心で安全な高度医療を提供。24時間体制による救急医療の提供や病院の施設・設備を共有できる体制、地域の医療従事者のために研修を行うなど、地域医療の中核を担う。また、質の高いがん治療を受けることができる地域がん診療連携拠点病院としての役割も大きく、外来化学治療センターを完備。緩和ケアの必要性も重視し、患者さんのさまざまな苦痛に対してやさしさと配慮をもった対応を行っている。
スープがつなぐ生きる力

「おいしいですね」とにっこりほほ笑む患者さん。先生たちもほっと安堵の様子。
料理研究家の辰巳芳子さんが、病と闘う自身の父親を思い、試行錯誤を重ねて生まれたスープがあります。それは「いのちのスープ」と呼ばれ、「生きること」や「愛」を伝える味として、広く知られるようになりました。いのちのスープを教える辰巳さんのもとには多くの医療従事者たちが集い、患者さんたちに食べる喜びや味わうことの尊さを伝えています。
京都第二赤十字病院もその一つ。穏やかな昼下がり、医師と調理師たちはある患者さんのもとを訪れました。ベッドサイドに運んだ白いポットから、ふわりと立ち上る香りが食欲をそそります。患者さんにとってはこれが5日ぶりの食事。喜びの中に一抹の不安が入り混じります。「もっと濃いのかと思っていたら、香りが良くてやさしい味。温かさもちょうど飲みごろね。これで体の調子も戻ってくれたらうれしいわ」。湯気の向こうの顔が思わず緩みました。患者さんの笑顔を呼び戻すスープ食の活動。それを支える医師、看護師、スタッフのみなさんに話をうかがいました。
―いのちのスープとの出会いを教えてください。

化学療法・緩和ケア部副部長 外科医長
柿原直樹先生
柿原先生 スープの考案者である料理研究家の辰巳芳子さんが、6年ほど前に緩和ケアを行う施設の医師や看護師などを集めて料理教室を開かれました。そこへ当院の緩和ケアチームを代表して僕と西谷さんとでおじゃましたのがきっかけです。
西谷さん 初めてスープを飲んだとき、素材の味が体中に染みわたって、ほっこりしたのを覚えています。仕込む工程を見せてもらうと、とても丁寧で細やか。きちんと計算された味なんだなあと驚きました。
柿原先生 塩分濃度が低いので、健常人の僕にはやや薄味でした。でも食材の旨み成分が強い。確かにおいしいスープだという印象が強く、自宅に帰ってすぐに実践しました。合間を見つけては玄米スープ、野菜のコンソメスープ、昆布スープの試作を重ねました。
―初めて患者さんに提供したのはいつですか。

外科副部長 NSTチェアマン 井川理先生
柿原先生 料理教室から半年後くらいです。がんで毎日嘔吐を繰り返している患者さんに僕が自宅でスープを作り、病院で温め直して持って行きました。なんとか口にでき「体に染みておいしい」と言ってくださったときはホッとしました。どんな薬を使っても抑えられなかった吐き気もその日は何か月かぶりになく、穏やかに過ごせて。患者さんは食べられないことを悲しんでおられたので、おいしいと言ってもらったときの笑顔は強く心に残りました。1週間後にまたスープを持って行ったのですが、そのときは死の間際。それでもひと口ふた口は飲んでくださって、数時間後に亡くなられました。
これがきっかけとなり、食事がとれなくなった緩和ケア患者さんを対象に、オプションサービスとして僕がスープを作ってベッドサイドに持って行くのが3、4年ほど続きました。みなさん死の直前まで飲んでくださって。
このことを栄養サポートチーム(NST)の井川先生に話すと、うちでも何か協力できないか考えてみようと言ってくださったんです。
井川先生 それまで緩和ケアの患者さんはNSTの対象外でした。NSTの活動の主たる目的は、入院患者さんの社会復帰を目指し栄養を改善すること。残念ながら緩和ケア患者さんは社会復帰が見込めないので…。でも私が今回、柿原先生からの話に納得できたのは、栄養改善には"心の栄養"も含まれるという点。緩和ケア患者さんにとっても最期まで味わうことは大事という考えに共感したので、このプロジェクトに参加しました。日ごろからさまざまな特別食を考えてきたNSTだからこそ、できることがあると思ったんです。まずはいのちのスープが病院のシステムとしてきちんと機能し、スープが必要と思った患者さんにいつでも出せるようにすることが大事だと。その一歩としてNSTでいろんな味を試作し、試飲会をしてアンケートをとったりもしました。
―スープの活動はチームの連携があってこそなんですね。

やさしい香りがする野菜のコンソメスープ。
柿原先生 はい。でも、院内に医療チームはたくさんあっても他チームと協力し合うことはなかなかないんです。NSTに相談させてもらったときも、現実になるとは思ってもいませんでした。たまたま井川先生と僕が消化器外科医同士だったことは大きいかもしれません。
井川先生 医局では、柿原先生と日ごろからよく雑談をしているので(笑)。
柿原先生 患者さんは心も体も病んでいるのに、食事が味気ないのは許せないというのが井川先生の持論。僕も全く同じ考えでした。僕らにとって、患者さんの食べる量は状態を知る一つのバロメーター。少しでも口にしてほしいというのが願いでもあります。でも緩和ケア患者さんにとって食べることは辛いことでもあるのです。そう考えると少しでも口にしてもらえる食材選びと調理法が大事。あとは環境ですよね。
―環境とはどういうことですか。
井川先生 いのちのスープの良さは手作り感。それがおいしさの秘訣でもあります。そこで患者さんにもっと喜んでもらうために、実際にスープを作った調理師さんをシェフと呼び、シェフが患者さんのベッドサイドで給仕することを提案しました。
柿原先生 こうすると、スープが病院食というイメージから離れ、患者さんはまるでレストランにいるみたいな気分になれる。少し環境を変えるだけで気持ちも変わります。案の定、患者さんには好評ですよ。
―作り手である調理師さん(シェフ)や管理栄養士さんたちはどういう思いを持っておられますか。

栄養課NST 調理師 増田勝彦さん
お盆にスープの入ったポットとマグカップを乗せてベッドサイドへ。これがいつもの給仕スタイル。
増田さん 毎回先生たちと一緒にスープを持って患者さんを訪ねますが、最初のころは緊張しました。
井川先生 調理師さんって日ごろは患者さんとの接点がないんですよね。
増田さん はい。だから大事そうに飲んでくださるのを間近に見て俄然やる気に。「他の味もあるんですか」と聞かれたり、トマト味のリクエストも出たり。うれしかったですね。
柿原先生 僕ら医師も調理師さんと会話をする機会はほとんどなかったので、医療のことをどれだけ熱く思ってくれているかわかっていませんでした。でも辰巳さんのスープの本を持って増田さんを訪ねたら20種類くらい本以外のスープも試作してくれて。僕らと同じ思いで仕事をしてくれているんだなあと心強かったです。
―今日は取材のためにスープをご用意いただきました。

栄養課NST 管理栄養士 山口真紀子さん
増田さん ニンジン、タマネギ、ジャガイモ、昆布、干しシイタケなどが入った野菜のコンソメスープです。澄んだ黄金色でしょう。このように仕上げるには鍋を触らないことが重要。火加減に気を配り、じっくり火を通して最後はガーゼで丁寧にこします。もちろん無添加。やさしい甘さの中にきちんと旨みが感じられて、患者さんに人気なんですよ。
山口さん 毎週月曜と水曜の提供日をみなさん楽しみにしておられます。5種類の味の中から患者さんに選んでもらった1種類をお出ししていますが、初めての人は万人受けする野菜コンソメかすまし汁を提供することが多いですね。
柿原先生 野菜のコンソメスープは野菜をカットする厚みまで決まっていて、手間がかかってこそ出せる味。本当に繊細なスープです。
―スープを作る際に気を付けていることはありますか。
山口さん 塩分です。始めたころは毎回塩分濃度を微調整して、患者さんに「今日は濃いね」と言われたときは記録をつけていきました。今はだいたい0.7%前後。通常の汁物は1%くらいなので少し薄いくらいです。和風の味もほしかったので、すまし汁をメニューに加えました。昆布はいいものを使おうと病院のコスト内で許されるものをいくつか取り寄せて吟味しました。
増田さん 普通のすまし汁よりは昆布の味が立っています。すまし汁は辰巳さんの本にもレシピはなく、当院のオリジナルです。
西谷さん 味覚障害があり食事がのどを通らなかったうどん屋の大将が「間違いない。これは店でも出せる」と太鼓判を押してくださったのがすまし汁。味覚障害がある患者さんに認めてもらえたことは自信につながりました。
―では、患者さんにスープを提供する際に心がけていることは。

看護部看護師長 緩和ケアチーム
がん看護専門看護師 西谷葉子さん
西谷さん 私はスープを提供する場に必ず同席し、患者さんの嚥下の状態を確認しています。安全に飲んでいただくことが何より大切なので。
増田さん 作り手としては温度ですね。最初のころは湯気が出ているのに勢いよく飲む患者さんが多かったので、やけどを心配しました。今は温度計のついたポットにスープを入れて運び、病態によって適温が違うので継続的にデータをとっています。
山口さん 器はあえて病院の食器を使わずに、花柄のマグカップに注ぎます。器にもこだわったのは、持ちやすさや飲みやすさに加えて、スープへの抵抗感をなくしたいという思いが強かったからです。
増田さん おかわりを希望される人は「今日中に飲んでね」と伝えてベッドサイドに置いて行くこともあるので、温め直せるようにふた付きでレンジ対応のものになっています。
―スープを飲んだ患者さんやご家族の反応はいかがですか。
西谷さん 患者さんのご家族にも一緒にスープを飲んでいただいていますが、とても喜ばれています。
井川先生 入院してしまうと、家族で同じ料理を囲み食事をすることがなくなるでしょ。おいしさは味うんぬんだけでなく"誰かと一緒に食べる"ということが大きいんですよ。
西谷さん スープ食には計り知れないパワーがあります。以前、全く口腔ケアをさせてくれず嚥下が乏しくなった終末期の患者さんがいらっしゃいました。でもスープならいけるかもしれないからチャレンジしようということになって。とにかく口の中をキレイにして、口に何かを入れることに抵抗感をなくしてもらって、まずすまし汁の香りを嗅いでもらいました。すると「おっ!」と良い反応が返ってきて、飲んでもらえたんです。それ以来活動も活発になって「~したい」という欲求も出てきました。
井川先生 絶食の患者さんは点滴で栄養は入れていても、食事を食べていないと無表情になってきます。食べられるようになると本当にイキイキしてきますよ。食材の旨みや味覚がきっと脳を刺激しているのだと思います。
―このスープ食の活動を通して、みなさんが学んだことはありますか。

マグカップに野菜のコンソメスープがゆっくり注がれていくと、辺りに良い香りが広がります。
井川先生 食事は栄養をとるだけでなく、その人の文化であり、生きていることを代表すること。スープを少し飲んだだけで栄養がつくわけではないですが、元気になるきっかけになるというのは感じます。
柿原先生 スープを持っていくと、どの患者さんも顔が和らぐんです。消えかかっている命の灯が、またぽっと灯るような。スープを飲んでいる間はしんどさも痛みもありません。このような瞬間に立ち会うと、医師は投薬したり手術をしたり、病気ばかりをみてしまいがちですが、それではダメなんだということを実感します。食事をとることで人間らしさを一瞬でも取り戻せるんですよ。緩和ケアの患者さんは使える薬も限られていますし、残念ながらその効果もほとんど得られません。そんなときに食や食を通してのコミュニケーションがすごい治療戦略になるんだと教えてもらいました。
山口さん 患者さんにとって食事は楽しみの一つなんですよね。それがカップにたった半分のスープでも。ずっと寝たきりだった人がスープのポットを見てむくっと起き上がる姿を見ると、食と人間がいかに密接にかかわっているかということがわかります。病院で普通に出す食事ももうちょっと工夫できればと思いますね。
増田さん 患者さんたちが両手で器を取って飲んでくださるのを見ると、感謝の心が伝わってくるんです。こっちがありがとうございますと言いたくなるくらい。こんな機会を作ってもらえて本当にありがたく思っています。その一方で、前回スープを持っていった患者さんが次はいらっしゃらないことも。今までは生と死を目の当たりにすることがなかったので、戸惑いもあります。
西谷さん 息を引き取る間際まで食べる喜びを伝えられるのが、このスープのすごさだと思います。まだ食べられることを実感することが生きている証。フルーツやおやつでなく、最期までスープという食事をいただくことに意味があるんですよね。
―この取り組みに対する今後の展望を教えてください。

消化器内科医長 緩和ケアチーム 河端秀明先生
山口さん 今は緩和ケアチームからの依頼を受けて特定の患者さんだけにスープをお出ししていますが、もう少し幅を広げて食欲不振の人などにも提供していきたいです。
柿原先生 終末期の患者さんだけでなく、広く入院患者さんに味わってもらって、おいしさを感じてもらえたらと思います。
河端先生 私は、このスープ食への取り組みを緩和医療学会で発表しましたが、聴講者からは良い反応をいただきました。スープ食の活動は他院でも実施されていますが、どこも良い結果が出ているようです。終末期を迎える患者さんはだんだん食べられなくなってくることで精神的にも参ってしまいます。私たちが食べる喜びとともに生きる喜びを伝えることが、患者さんの苦痛を和らげる一助となると信じています。
―今日は貴重なお話をありがとうございました。