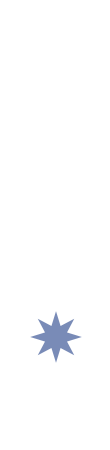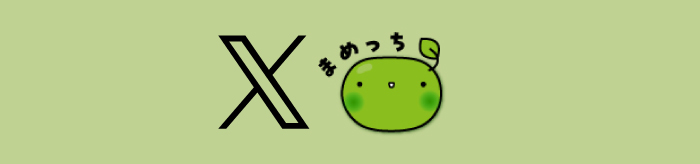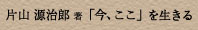京都府立桂高等学校
古都の豊かな食文化を長きにわたってけん引してきた伝統野菜たち。他の野菜とは一線を画す野趣あふれる香りと独特な味わいは、調理を施しても霞むことはなく、口の中で存在感を放ちます。しかしその際立った個性が足かせとなり、時代の波に押されて多くの品種が姿を消しつつある今。高校生たちによる守る取り組みを追いました。

京都府立桂高等学校
京都市西京区川島松ノ木本町27 075-391-2151
http://www.kyoto-be.ne.jp/katsura-hs/
「創造性に富み、心豊かな、たくましい人間の育成」を教育目標に掲げる同校は、1948年に創立。最大の特徴は、普通科に加え農業や植物に関して学ぶ専門学科を設けているということ。園芸ビジネス科は農業の基礎知識を身につけ、スペシャリストの育成に注力。野菜や草花の栽培から販売までを行う。また植物クリエイト科では、植物の育種から生産・加工に至るまでの知識や技術を習得。バイオテクノロジー技術を応用した学習も取り入れている。2012年にはスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)指定校に認定。先端的な技術や高度な技能を磨き、研究活動も積極的に行っている。
移りゆく京野菜の実情

イキイキと育った伝統野菜たち。土づくりは先生が担当。化成肥料は使わず減農薬を心がけています。
京野菜は京都府内で取れた野菜の総称であり、認定されているのは43品目。その中でも、京都府全域で明治以前から栽培が続いているものを「京の伝統野菜」と位置付けています。京野菜が特産品として独自の進化を遂げ、確固たる地位を築き上げた背景には、より良質を求めた公卿や貴族の食生活と、精進料理への需要拡大があったともいわれています。
聖護院かぶや堀川ごぼうなど、産地の名前がつけられている京野菜たち。地域と深く結びつき、作り手たちの汗により長い歴史の中で多くの品種が生まれてきました。しかし現在は、環境の変化や時代の移り変わりにより徐々に衰退へと向かっています。特に京の伝統野菜を取り巻く現状は深刻。栽培方法が難しく害虫や病気に弱いため安定した収穫が見込めないことや、食の欧米化による需要の先細りなど、多くの問題を抱え作り手が減少。すでに絶滅してしまったもの、また絶滅の危機に陥っている品種もあります。今かろうじてつながっている命のバトンを次世代に渡していきたいと、名乗りを上げたのが京都府立桂高等学校(以下桂高校)の生徒たちでした。
実りを迎えた晩秋の畑へ

生徒たちは農作業に一生懸命。害虫対策など栽培方針は先生と相談しながら決めていきます。
桂高校の校内には、京の伝統野菜を栽培するために整備した畑があります。管理を行っているのは植物クリエイト科・園芸ビジネス科京の伝統野菜を守る研究班の生徒たち。桂高校ではスペシャリスト教育の一環として、2、3年生になると12ある研究班のいずれかに属し、興味のある分野をより深く掘り下げられる学習スタイルを取り入れています。京の伝統野菜を守る研究班もその一つ。現在は2年生12人と3年生8人の計20人が活動し、週3時間の授業に加え、放課後や休日も畑に出で伝統野菜の管理をしています。
11月中旬のある日。「そろそろ冬の野菜が実りの時期を迎えていますよ」と記者に声をかけてくれたのは、研究班の生徒たちを指導する松田俊彦先生。カメラを手に急いで畑へと向かいました。まだ午後2時ごろだというのにすでに陽が傾き始めた晩秋の畑では、金時人参やすぐき菜などが勢いよく葉を広げています。現在、桂高校で栽培している京の伝統野菜は14種類。生徒たちは畝と畝の間に腰を据え、間引きの作業をしていたり、除草をしていたり。背中を丸めながら黙々と畑仕事に勤しんでいました。その手を止めて取材の案内役を買って出てくれたのは、2年生の古田萌黄さんと瀧瀬楓子さんです。
伝統野菜の代表格「九条ねぎ」

シャキッと元気よく育った黒種の九条太ネギ。冬にかけてますます長く太くなるのだそうです。
「たくさん育てている伝統野菜の中でも、私たちが今一番力を注いでいるのが九条ねぎです。ちょうど食べごろなんですよ」と畑を指さす古田さん。どっしりと大地に根を下ろし、深い緑色の葉がイキイキと空に向かって伸びています。その1本1本が普段スーパーなどで売られているものより立派で、目を見張るほど極太。長さも1mを超えています。「実は九条ねぎには2つの種類があるんです」と古田さん。それぞれの特徴を教えてくれました。「飲食店や家庭などでもよく使われている一般的な品種は浅黄系と呼ばれるもの。やや細身なので九条細ねぎともいいます。私たちが栽培しているのは黒種系です」。さらに瀧瀬さんが「成長すると1.5mの長さにまで達し、直径が缶コーヒーくらいまで太くなることもあるんですよ」と続けます。
黒種系は九条太ねぎともいわれている希少種。霜が降りて寒さが深まると、葉の中に透明でヌルヌルとした「あん」が増大し、甘味とうま味が増します。普通のネギより柔らかいのもおいしさの秘訣。その反面、「背が伸びすぎるとささいなことで倒れたり折れたりすることもあり、売り物にならなくなるんです」と古田さん。転倒防止のロープを畝の両サイドに渡すのも、生徒たちの大事な仕事です。
手間をかけて育ててこそ

柔らかすぎるために大きく育つと折れてしまうこともたびたび。こうなると商品にはなりません。
京の伝統野菜としての九条ねぎは、もともと浅黄系より黒種系が主流でした。しかし今では黒種系を栽培する農家が激減。市場でもめったに見かけないことから、地元ですら存在を知る人が少ないといいます。時代とともに黒種系の影が薄くなっていったのにはいくつか理由がありました。
まず一つに、栽培期間が1年以上を要し、非常に手間暇がかかる野菜であること。桂高校で黒種系の種まきを行うのは収穫前年の10月初旬。冬を越え、春を過ぎ、初夏のころに育った苗を一度掘り上げて干します。こうすることで暑さを嫌う苗を直射日光から防御。同時に養分をたっぷりと貯め込ませます。そして暑さが和らぐ夏の終わりにまた畑へと戻す作業を開始。11~3月に成長のピークを迎え、ようやく質の良い九条太ネギが収穫できるのです。
これほどまでに手をかけて育てても、長く柔らかすぎるために今の流通システムには向きません。加えて、一般的に青ねぎは細くて薬味に用いるものというイメージが根強いため、太すぎて薬味に不向きな黒種は需要が低め。市場価値も自然と下がってしまいました。
見た目を裏切る唐辛子

真っ赤に色づき、まさに食べごろの鷹ヶ峯唐辛子。甘くみずみずしく、肉厚で食べ応えは充分です。
「これを食べてみてください」。九条ネギの次に案内された畑で瀧瀬さんがおもむろに差し出したのは、大きくて真っ赤な唐辛子。なんとも辛そうな見た目に恐る恐る少しだけかじってみると、厚みのある果肉は予想を裏切るフルーティーな甘さ。辛さなどどこにも感じられません。「これは鷹ヶ峯唐辛子と呼ばれる甘い唐辛子なんですよ」。
鷹ヶ峯唐辛子は人々の嗜好の変化に合わせて生み出され、明治以降に品種として確定した京の伝統野菜に準じる野菜です。実り初めは艶やかな緑色をしていますが、畑で成熟させていくとはっとするほど鮮やかな赤色に変化していきます。見た目にインパクトがある味わい深い野菜ですが、収穫率が低く栽培地もごくわずか。市場で見かけることはほぼありません。
「絶滅寸前だと聞いて、私たちの手でどうにか守っていけないかと考えました。ありがたいことに農家さんが大事にされていた種を譲ってもらうことができ、栽培するようになったんです。ただし実は売らず、種も一切外には出さないというのが、その農家さんとの約束。今は研究のためだけに育てています」と古田さん。種を取った後は生徒たちが家に持ち帰り、じゃこと炒めたりカレーの具にしたりして食べているそうです。なんともうらやましい話。ぜひとも再び市場に広がってほしい味わいです。
栽培から販売までが学び

振り売りに出かける生徒たちの台車には収穫したばかりの野菜がいっぱい。地域の人たちにも大変好評だそうです。
放課後、授業を終えた生徒たちはその日収穫した野菜を台車いっぱいに乗せ、いそいそと準備に追われている様子。聞けば、今から校内や地域を売り歩いて回るとのことでした。これは伝統的な行商である「振り売り」になぞらえたもの。京都では昔、農家の女性たちが収穫したての季節の野菜を大八車や頭に乗せたかごに入れて売り歩いていました。常連さんの家に声をかけると、自然と近所の主婦たちが寄り集まり、旬の味を買い求める光景が街中で見られたそうです。今よりずっと生産者と消費者の距離が近く、本当の意味で“顔の見える販売”が行われていました。
栽培した野菜を売ることも、生徒たちにとっては大事な仕事であり学びの場。自分たちが作ったものに顧客が魅力を感じ買ってくれてこそ、野菜を育てることに意味が生まれると松田先生は言います。
「地域を回っていると、『今日は何を売っているの?』『こないだの、おいしかったよ』と声をかけてもらえるのがうれしくて」と声を弾ませる瀧瀬さん。売り上げは肥料や資材を購入する資金になります。稼がないと来季の野菜をつくることができなくなるので生徒たちも必死。古田さんは栄養面から野菜の魅力をアピールするなど、消費者に響く売り文句にも頭をひねっているそうです。
始まりは水菜の種から

見せてくれた小さな小さな種。
四季折々ににぎやかな顔を見せてくれる桂高校の畑。ここで京の伝統野菜づくりがスタートしたのは8年前のこと。松田先生によれば、きっかけはある日手にした水菜の種だったそうです。
「授業の一環で京野菜の水菜を育てようと種を買ってきたところ、その袋には採種地名が中国と記載されていました。気になって他の京野菜の種の袋も見てみると、どれもこれも諸外国ばかり。日本の野菜なのにどうしてだろうと疑問を抱いたことから、生徒たちとともに調査を始めました。調べていくと、京野菜のほとんどが固定種ではなく、F1種(交配種)であることがわかったんです」。
現状に触れて危機感を覚えた松田先生と生徒たち。このまま放ってはおけないと、府内で固定種から伝統野菜をつくっている農家さんを探し出し、少しずつ種を譲ってもらい栽培に取り組むことにしました。けれども、その種を手に入れるまでが難関。一筋縄ではいきませんでした。
シードバンクとしての役割

伝統野菜以外にもえごまといぐさを栽培。えごまはα-リノレン酸を多く含むという優れた作用に注目し研究中。
「本来の伝統野菜は固定種なので、種から農家ごとに異なる個性がありました。そのうえ土の状態や栽培方法が違うのですから、同じ品種の野菜でもおのずと出来上がった味に差が生まれるわけです。農家は振り売りの際にごひいき筋から味に対する評価を聞き、好まれる味の種だけを残してさらに良いものを栽培する努力を続けてきました。苦労して改良を重ね、先祖代々受け継いてきた種は門外不出。家の家宝として扱われていたのです」。
そのため、松田先生や生徒たちがいくら頭を下げても最初は全く取り合ってもらえませんでした。門前払いが続いても粘り強く働きかけを行ったのは「当校が将来的に伝統野菜のシードバンク機能を果たすことができればという思いもあったからです」。
生徒たちのひたむきな努力と成果が世間で認められ始めた今は、農家のほうからすすんで種を譲ってくれる機会も増えました。人から人へとつながれていく温かな種のリレーが、京の伝統野菜の明日を切り開いています。
伝統食を継ぐ未来の瞳

案内役の古田さん(上段左)と瀧瀬さん(上段右)。企業が見学に訪れた際もガイドをするらしく、説明は完璧でした。 「買ってください。おいしいですよ!」という振り売りの声に記者も思わず野菜を購入してしまいました(下段)。
京の伝統野菜づくりを通して、毎日貴重な経験を重ねている生徒たち。ときには育てた野菜をツールにビジネス関連のコンペティションに参加することもあります。市場のグローバル化が進む中、今後は栽培した野菜の付加価値をどうつけていくかも大きな課題。「伝統野菜は大量に売れるものではないですし、農家さんたちが独自で市場を開拓することはなかなかできません。この厳しい状況を生徒たちが若い力で打開してくれればうれしいです」と松田先生は期待を寄せます。
何かと忙しい毎日でも、古田さんと瀧瀬さんは「野菜づくりはやりがいがあって楽しい」と顔を見合わせてニッコリ。それも年頃の女子高校生には畑仕事で辛いこともあるのでは? 「夏は朝の7時半から、冬は7時45分から畑で観察と収穫を行います。特に寒いときは朝が早いのがちょっと大変ですね」と苦笑いの古田さん。瀧瀬さんは「桂うりは実が重いうえに葉っぱに小さなトゲがたくさんあって痛いのでちょっと苦手。夏の炎天下での収穫にも苦労します」とかわいらしい一面をのぞかせました。
古田さんは農業大学に進学し、野菜栽培についてもっと深く学ぶのが目標。瀧瀬さんは小さいころから山や自然が大好きなアウトドア女子。森林学科のある大学で自然や植物の魅力を追求していきたいと、キラキラした目で夢を語ってくれました。